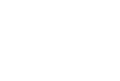家は住む人の暮らしをつくり、
暮らしは人生をつくる
かけがえのない日々のその瞬間
人も環境もありのままでいられること
人と家が波紋のように自然に響き合うこと
そんな豊かな建築を目指しています

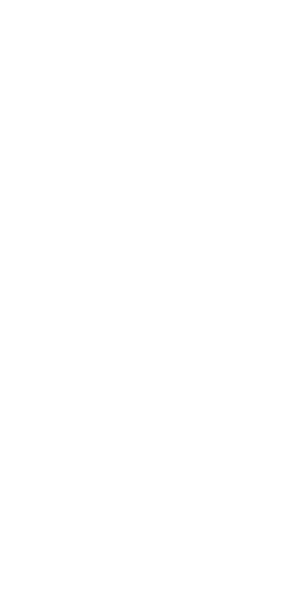
光と影、風の香り、
雨の音、木々のゆらめき。
人の心はいつも、自然とつながっています。
自然の変化を空間へ取り入れる。
私たちは、その土地がもつ魅力を大切に、
暮らしと環境が溶け合う空間を考えます。
BUSINESS DETAILS
建物の用途、規模、構造などの制約はなく、幅広い設計に対応しています。
インテリアの提案や庭のデザインなど、さまざまなご相談や依頼を承ります。
WORKS
これまで手がけた様々なプロジェクトをご紹介しています。
住宅、店舗、ホテルなど、幅広い分野でのデザインをお確かめください。過去の実績をご覧いただけます。
-
- RESIDENCE

継承する家 – 宮古島市 (2023) -
- VILLA

波癒 ~ Namyu the place – 宮古島市 (2021) -
- OTHERS

首里の集合住宅 – 那覇市 (2018)
WORKFLOW
お客様の夢とビジョンを現実にするために、
私たちは以下のステップに沿って、丁寧なワークフローでサポートしていきます。
REAL ESTATE
未活用の土地を有効活用し、不動産業を展開しております。
その土地を最大限に活かした、独自のデザインと建築アプローチをご提案させていただきます。(現在準備中です)


様々な情報をInstagramで発信しています。弊社の情報などを随時UPしております。
KISETSU
沖縄在来の植物をつかい、自然と調和したお庭・ランドスケープのデザイン。
人間が本能的にもっている自然への愛や親しみ=バイオフィリアを生活に取り入れる提案をしていきます。
CONTACT
建築やデザインに関するご質問やご相談がございましたら、
以下のフォームに必要事項をご入力の上、お気軽にお問い合わせください。
当設計事務所は、法人様から個人の方まで幅広いニーズに対応しております。
ご記入いただいた情報は厳重に管理し、プライバシーを尊重して取り扱います。
(個人情報保護方針)